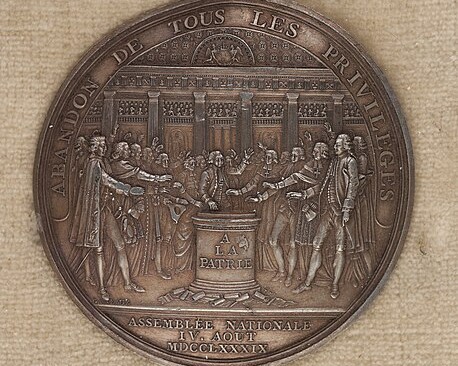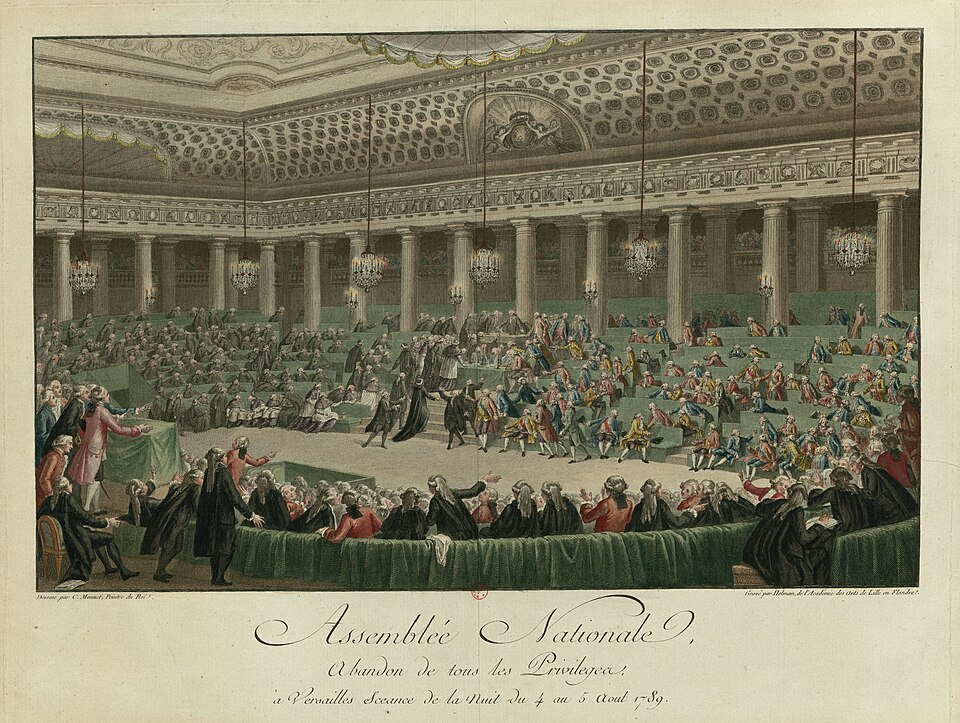フランス革命でフランスの身分・階級制度はどう変わったのか?
フランス革命は、国のしくみをひっくり返しただけじゃなく、社会の土台にあった身分制度そのものを大きく変えてしまった歴史的な出来事です。
当時のフランスでは、人々は第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)、第三身分(平民)の三つに分けられていて、上の身分にいる人たちほど多くの富や権利を持っていました。一方で、人口の9割以上を占める第三身分の人たちは、重い税を課せられながら政治に口を出すことすら許されない――そんな不公平きわまりない社会構造が当たり前だったんです。
こうした不満が積もりに積もって、ついに爆発。封建的な身分制度を壊そうという動きが、革命の大きな原動力になっていきました。
ここからは、革命前の身分制度がどんな仕組みだったのか、そして革命によって何がどう変わったのかを、もう少し詳しく見ていきましょう。
|
|
|
基本の社会階級
フランス革命の大きな引き金になったのが、当時の社会に根深くあった「身分制度のゆがみ」です。人は生まれた瞬間から身分が決まっていて、それが税金の重さ、職業の選択、政治への関わり方にまで影響していたんです。
特権を持つ人と、そうでない人とのあいだには、越えようのない大きな差がありました。その不公平さが長いあいだ積もり積もって、ついに爆発した――それがフランス革命だったというわけです。
特権身分
革命前のフランスでは、第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)が特権身分として社会のてっぺんに君臨していました。
彼らは税金をほとんど払わず、広大な土地を所有して、富や権力を思いのままにしていたんです。
第一身分の聖職者は、教会を通じて人々の生活に深く関わり、教育、結婚、死にいたるまで、あらゆる場面で影響を持っていました。国家に宗教的な正統性を与える存在としても重宝されていたんですね。
一方、第二身分の貴族たちは、軍隊や政治の中枢を担当し、王の側近として国家運営に関与。地方では農村の領主として君臨し、農民から年貢を取り立てて暮らしていました。
つまり彼らは、「信仰」と「武力」という二つの大きな柱で、社会を上からぎゅっと押さえ込んでいたんです。
非特権身分(平民)
それに対して、第三身分(平民)は、あらゆる意味で不利な立場に置かれていました。ここには農民、都市の職人や労働者、さらには経済力を持ち始めた中産階級(ブルジョワジー)まで含まれていて、立場はさまざまですが、どの層にも共通していたのが「搾取されている」という感覚でした。
特に農民たちは、領主への地代、教会への十分の一税、国家への直接税という三重苦を背負い、日々の暮らしは常にギリギリ。都市の労働者たちは、パンの値上がりに苦しみ、物価高に泣かされていました。ブルジョワジーは経済力こそあれど、政治への参加が認められないことに強い不満を抱いていたんです。
こうした平民たちの怒りと焦りが一気に爆発し、やがて社会の根本を揺るがすフランス革命という大きなうねりを生み出していくことになります。

三身分
フランス革命前の税負担を初めとする不平等な社会構造を風刺した絵画。快適に座る貴族と聖職者(第一身分と第二身分)と、その下で労働を背負う第三身分が描かれている。。
(出典:Creative Commons Public Domainより)
上に立つ者が優遇される一方で、下にいる者だけが重荷を背負う。そんな社会のゆがみは長年放置されるうちに不満を膨らませ、ついには「革命」という爆発を生んでしまいました。言い換えれば、フランス革命は身分制度そのものを揺るがす挑戦だったんです。
革命前の身分制度
すでに見てきたように、フランス革命の直前まで社会は「三つの身分」によってがっちり区切られていました。この仕組みでは、人の暮らしや権利が生まれながらに決まってしまうんです。
しかもこの制度、身分のあいだの移動がほとんどできない閉ざされた世界。少数派の特権身分が大多数の人々を支配するという、どう見てもアンバランスな構造でした。そんな不公平さが不満を積み重ね、やがて「革命の火種」となっていくんです。
第一身分
第一身分は聖職者。人口の1%にも満たないごくわずかな人たちでしたが、なんと国土の約10%を持っていたんです。しかも免税の特権があり、農民からは十分の一税(収穫の1割!)を徴収。さらに寄付金まで加わって、経済的にもかなり豊かな層でした。
宗教的な権威を背景に、「社会秩序を守る」なんて役割を果たしていた彼らですが、啓蒙思想が広まり、経済も苦しくなる中で、だんだんその立場が揺らぎ始めていたんですね。
第二身分
続いて第二身分は貴族。こちらは人口の約2%ですが、国家の高い役職をほぼ独占していました。地方では封建的な年貢を取り立てるなど、庶民を支配する立場にもありました。
ヴェルサイユ宮殿に出入りする宮廷貴族たちは、豪華な生活を楽しむ一方で、地方に残る田舎貴族は収入が減って困窮することもあり、貴族階級の中でも格差が広がっていたんです。この格差が原因で、貴族の間でも摩擦や不満がくすぶるようになっていきました。
第三身分
そして最後に第三身分。なんと人口の約98%を占める、まさに社会の大多数です。農民や都市の労働者、そして商工業で成功したブルジョワジーといった中産階級まで、さまざまな層が含まれています。
中でもブルジョワジーは、商売や製造業で大きな経済力を持つようになっていましたが、政治の世界では冷遇されていて、そこに強い不満を感じていました。一方で農民や労働者たちは、重税・労働義務・食料不足に苦しみ、生活は常にギリギリ。
とくにパンの値段が上がったり、凶作で食べ物がなくなったりすれば、すぐに暴動につながるほど不安定な暮らしだったんです。
この第三身分の「自分たちばかりが損をしている」という怒りが、フランス革命を突き動かす最大のエネルギーとなっていったんですね。
以上、フランス革命と身分・階級についての解説でした!
ざっくりと振り返れば
- 第一身分と第二身分が特権を享受していた一方、第三身分が重い負担を負っていた
- 社会的不平等が革命の引き金となり、特権身分の解体が進んだ
- 平民の声が新たな社会秩序を生む重要な役割を果たした
・・・という具合にまとめられるでしょう。
ようは「フランス革命は不平等な身分制度を打破し、社会の基盤を劇的に変革した。」という点を抑えておきましょう!以下でフランス革命期の身分・階級に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。
|
|
|